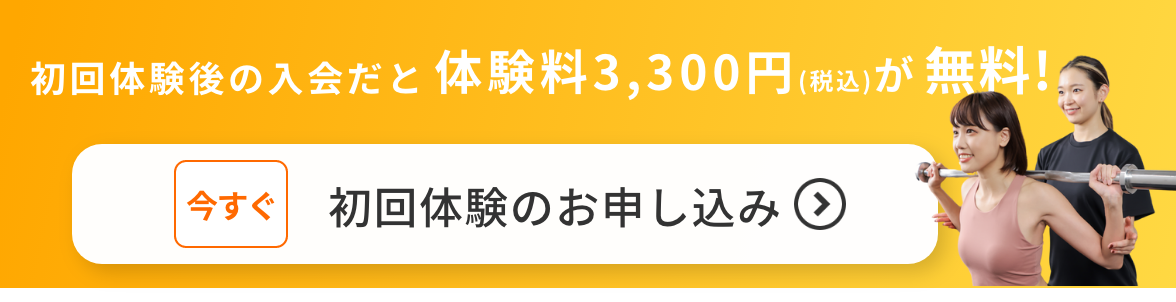健康維持や運動のサポートに飲む方が増えているプロテイン。
「飲み始めてからお通じが悪くなった。」
「便秘だけでなく下痢をしやすくなった。」
このようにプロテインによるお腹の不調について聞いたことがある人や、実際に体感して不安になっている方もいるかもしません。
忙しい方に向けて、結論をまとめてお伝えします。
現在のところプロテインが直接便秘を引き起こすとまでは断言されていません。
ですが、高たんぱく+低繊維食が腸内環境を悪化させて便秘リスクが上がることがあることがわかっています。
この記事では、プロテインで便秘(お腹の不調)になると言われる理由や対処方法など、プロテインと便秘の関係性をご紹介しますので、ぜひ確認してみてください。
便秘のメカニズムと腸内環境
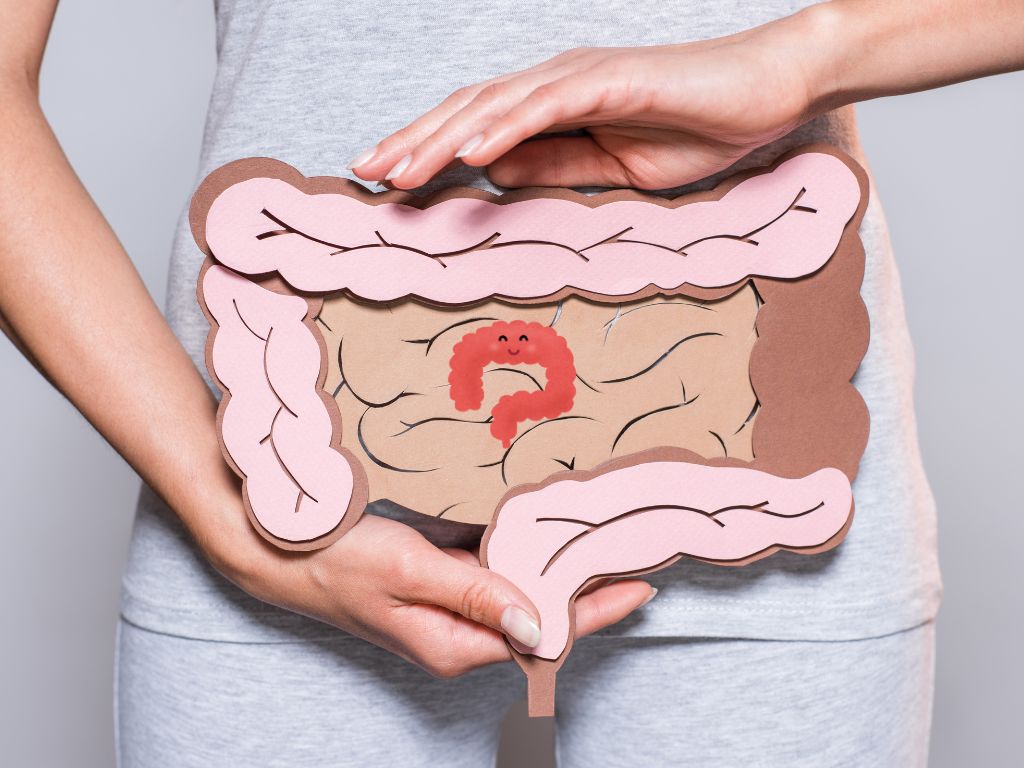
便秘を経験したことがある方は多いと思いますし、症状もご存じだと思いますが「そもそもなぜ便秘になるのか?」を意識したことがあるでしょうか?
病気や体の異常による便秘(器質性)もありますが、腸内のバランスの悪化にともない大腸の機能が低下することでおこる機能性便秘が、いわゆる一般的な便秘と認識されています。
腸内環境の悪化を招くのは、とても身近な日々の生活習慣が原因です。
水分不足・運動不足・ストレス
大腸は小腸で消化された後の残りから、水分を体内に吸収します。
この時に水分が不十分だと、便自体が硬くなるとともになめらかに腸から体外に移動しにくくなるため、排便の回数が減るわけです。
また腸の動き(ぜん動運動)が弱くても、便を外に押し出す力が足りなくなり便秘になります。
ぜん動運動を活発にさせるためには、運動をして外から腸を刺激してあげるほか、ある程度の腹筋の強さが必要です。
なにかと万病の元にされやすい「ストレス」についても、やはり便秘の原因の一つになり、腸の働きを抑えてしまうことがあることをご存知でしょうか?
これは、様々な原因で心身に強い負荷を感じるストレス状態が続くと、自律神経(※)が乱れて交感神経が優位になる(体の動きを優先、消化機能を抑える状態)ことが関係しているようです。
※自律神経とは、交感神経(体の動きが優先、消化機能度が抑えられる状態)と、副交感神経(リラックした状態、体内活動が活発化する状態)があり、自分の意思とは関係なく働く神経。
バランスが大切!悪玉菌と善玉菌
腸内には無数の細菌がありますが、主に善玉菌と悪玉菌、そして日和見菌(善悪どちらの性質でもない菌)に分類されています。
【腸内細菌の理想的なバランスと役割】
| 善玉菌(約20%) | 悪玉菌(役10%) | 日和見菌(約70%) |
| ビフィズス菌、乳酸菌など 腸内を酸性に保つ(※) 病原菌の増殖を抑える ビタミン合成や免疫調整にもかかわる | 大腸菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌など 腸内をアルカリ性に傾ける 腐敗産物(アンモニア、硫化水素)を作る 増えすぎると便秘・肌荒れ・免疫低下を招く | 普段はこれといった働きをしない 善玉・悪玉いずれか優勢な方の見方につく 腸内環境のバランスを左右する「中間勢力」 |
上記の通り善玉菌はお通じを含め体に良い効果を与える細菌ですが、悪玉菌は腸の中を腐敗させる物質を作ることで腸内環境を悪化させ腸のぜん動運動を弱める細菌です。
腸は栄養の消化吸収だけではなく、免疫機能・ビタミンの合成なども担う大切な器官であり、善玉菌が多い状態を保つことは健康維持にかかせません。
詳しくは後述しますが、プロテインを積極的にとっている方の場合、意図せずに「高たんぱく+低繊維食」という偏った食事内容になることがあります。
この場合は悪玉菌の増加を手助けしてしまい、結果として便秘のリスクをあげてしまう可能性があるでしょう。
※善玉菌は腸内が酸性の方が活動しやすく、悪玉菌は逆に増えにくくなる(有害物質が少ない)ため、酸性に保たれる方が腸内環境が良好と言える。
なぜプロテインが便秘につながるのか?

初めにお伝えした通り、プロテインが直接便秘を起こすとまでは断言されていませんが、個人の体質や条件がそろえば便秘のリスクををあげる傾向があるとされています。
プロテインを飲む量や種類(動物性・植物性)もお腹の調子を崩してしまう原因になりますので、プロテインを飲み始めてからお腹の不調を感じる方の場合は、特に注意が必要です。
動物性プロテインは悪玉菌が増えやすい
悪玉菌が増えすぎるとお腹の調子を悪くさせ便秘のリスクをあげてしまうことは、先にお伝えしたとおりです。
タンパク質の中でも肉や魚といった動物性タンパク質は、悪玉菌のエサになります。(※)
ですが、悪玉菌を増やすとはいえ動物性タンパク質も必要な栄養素であり、適切な量であればきちんと消化されて悪玉菌が一気に増えるという状態にはなりません。
※正確には動物性タンパク質を分解する時に発生する窒素=有害物質が悪玉菌を増やす餌になる。
消化力は個人差あり!プロテインの飲み過ぎはNG
動物性の材料を使ったプロテイン(ホエイ)で過剰にタンパク質をとると、消化しきれずに大腸に残ったタンパク質が悪玉菌のエサになると説明しました。
簡潔にいえば、プロテインの飲み過ぎや動物性タンパク質の摂りすぎは、悪玉菌を増やす手伝いをしているようなものです。
なおかつ1度に消化吸収できるタンパク質量には限度がありますので、必要以上に飲んでも筋肉の維持や体作りにはあまり活かされず、かえって腸内環境が悪化しやすくなります。
そのためプロテインを飲む場合は「食事から取るタンパク質量」も含めて、適正な量をとるようにしてください。
無理はしない!腸内環境を整えてプロテインを摂取する方法

プロテインを飲んでいる方の多くは、体づくりや栄養補給、健康維持など「ご自身の体と健康」を意識している人だと思います。
日本人の食生活は、そもそもタンパク質不足になりやすいと言われており、意識してタンパク質を取ることは重要ですが、栄養バランスを保つことも必要です。
腸内環境を良好に保ち便秘を防ぐために以下の項目を意識すると良いとされています。
- 食物繊維(便の量を増やす)
- 水分(便を柔らかくする)
- 運動(ぜん動運動を活発にさせる)
- 腸内環境ケア(善玉菌を増やして、腸内環境を健康に保つ)
- プロテインの量と種類見直し
細かいように見えますが「1つの栄養素に偏らない」「水分をしっかり取って適度に運動(腸を刺激して活動をうながす)する」といった健康的な生活を目指すことが、便秘のリスクを上げないポイントと言えるでしょう。
関連記事:女性がプロテインを飲むと太る?摂取タイミングや選び方のコツを解説
生活習慣・全体的な食事バランスの見直し
リアルフードでもサプリ(プロテイン)でも、タンパク質をしっかり取ることに意識が偏りすぎると、食物繊維が不足してしまうことがあります。
食物繊維は成人男性21g以上/女性18g以上とり、水分は1日あたり1.5〜2.0Lが目安です。
食物繊維は野菜・果物・豆類・海藻・オートミールなどに多く含まれるので、肉や魚をメインにした場合は、副菜や汁物に加えるなど、複数回に分けてうまく食物繊維をとり、水分補給も行いましょう。
腸内環境を良くするためには、善玉菌の数を増やす(悪玉菌より多い状態にする)=発酵食品やオリゴ糖などを食事に取り入れることがポイントです。
運動については運動習慣がない方はそもそも腹筋が弱かったり、腸に対して外からの刺激がなく、ぜん動運動が弱くなっている可能性があります。
腸の動きを促すことがスムーズな排便につながるので、ウォーキングや軽い筋トレなど運動の習慣化も試してみてください。
また、便秘や腸内環境にかかわらず、規則正しい生活習慣は体の調子全体を整えるために必要です。
時間を決めなくても良いので、「便意がなくても朝食後はトイレに行く」など一定のリズム・ルールでトイレにいく習慣づけを行い排便リズムを整えることも便秘リスクを下げるために有効です。
関連記事:ウォーキングに痩せる効果はある?結果に導くダイエットのコツを解説!
関連記事:【初心者必見】自重トレーニングで理想的な体を手に入れる方法8選
プロテインの種類と飲む量を調整
適正な量の範囲でプロテイン飲んでいても、食べ物の消化力は個人差があるので便秘の症状が出る場合も推測されます。
便秘の原因は様々あるので、本当にプロテインが便秘の原因なのかは判断しにくいと思いますし、自己判断を信じすぎるのも危険です。
あくまでも、目安(プロテインがお腹の不調に関係しているかを調べる)ではありますが、以下の方法を試してみてください。
プロテインを飲む前は調子に問題がなかった人であれば
- 一旦プロテインを飲む量を減らす
- 種類を動物性(ホエイ・カゼイン)から、植物性(ソイ)に変更する
- プロテインを飲むのをやめる
上記1からはじめ、便秘の改善がなければ2・3に進んでみて、便秘の症状が改善するかを確認してみてください。
便秘や下痢が長引くなら医療機関へ相談
生活習慣をできるだけ改善したり、市販薬を試してもお腹の不調が改善されない事があります。
便秘や下痢などお腹の不調がプロテイン起因の場合もありますが、量・種類の変化・飲むのを一旦やめても調子が戻らないようであれば、原因は別にあるかもしれません。
この記事でも一般的な便秘の原因や対策をご紹介したとおり、情報を調べることができますが「結局のところお腹の不調がなんであるか?」は、ネットの知識だけでは突き止められませんし、自己判断を過信するのは危険です。
便秘や下痢が長引く場合は放置せずに医療機関へ相談してください。
【便秘を恐れない】プロテインを上手に活用して健康維持を目指そう

この記事ではプロテインを飲むと便秘になるのか?という問題にフォーカスして、プロテインと便秘の関係性、なぜお腹の調子を崩すのか?対策はあるのかを、まとめていきました。
「プロテインを飲むことが原因で便秘になる」とまでは断言はされていません。
しかしながら、高たんぱく(動物性プロテイン)+低繊維食が腸内環境に悪影響(悪玉菌を増やしやすくする)してしまい、便秘のリスクをあげてしまうことがあります。
ですが、プロテイン自体は体づくりや健康維持のためにも必要な栄養であるため、便秘を恐れて控えるのはお勧めできません。
プロテインを適正な量を飲みつつ栄養バランスが偏らないようする、健康的な生活(便意を我慢しない、排便リズムを作る、ストレスを溜めない、軽い運動をする)を送ることが大切です。
当ELEMENTジムは健康的な生活を目指したい方を「時短トレーニングの習慣化×個別指導」でサポートします!
トレーニングのプロ(または早期資格習得を目指すトレーナー)による、あなたの目的にあわせたプログラムで一緒に健康を手に入れませんか?
健康や体づくりのお悩みがあれば、ぜひ体験レッスンに参加してご相談ください。
体験は随時開催しているので、お気軽なご参加をお待ちしています。