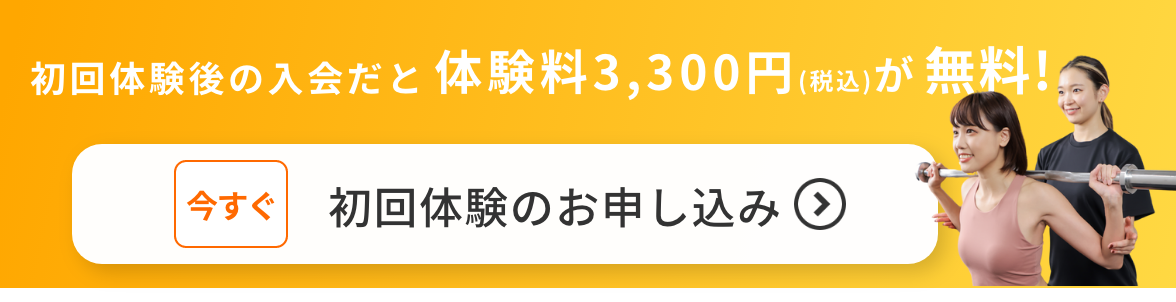風邪を引いた時に「プロテインは飲んでいいの?」
それとも「飲まない方がいいのか?」
普段からトレーニング(体づくり)や健康維持でプロテインを摂取している人は、ふと気になるテーマだと思います。
結論からお伝えすると、風邪のときは無理にプロテインを飲まなくても良いと言えます。
プロテインを飲む・飲まないで悩まずに、胃腸に負担をかけず消化吸収が良い食事をとり、しっかり休んで風邪の回復に専念するのが大切です。
ただし、タンパク質は免疫細胞の材料であり、日頃から十分にとることで免疫維持に役立つので、風邪予防(一般的な体調管理)や、症状の程度によっては風邪罹患時にとるメリットもゼロではありません。
そこで、今回はプロテインと免疫の関係・風邪の時の飲むメリットとデメリットをまとめてご紹介していきます。
ただし当記事の筆者は医療従事者ではありませんので、風邪が長引いたり症状が重篤な場合の対処(食事やサプリメントの摂取)については、必ず医療機関に相談してください。
プロテインを摂取する基本的なメリット
プロテイン製品を摂取する一番大きいメリットは、手軽にタンパク質が取れることです。
トレーニーやダイエット・健康維持など、目指す目的は違えど食事の「PFCバランス」を意識したことがある方なら、思い当たることがあると思います。
「食事から1日に必要な量のタンパク質を取ることは意外と難しい」ということに。
また、あまり意識されないメリットとして、免疫の維持もあげられますので把握しておきましょう。
手軽にタンパク質が補える
3大栄養素であるタンパク質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)をバランス良く、3回の食事から必要な量とることが理想です。
ですが、高タンパク質の食材は高カロリーなものも多く、タンパク質の必要量だけ気にしていると食事全体のカロリーが上がる=食べ過ぎになりやすい傾向があります。
また、食事量が少ない方(加齢による減少や、多忙や生活習慣により欠食しやすい)も、タンパク質不足になりがちです。
プロテインはドリンクタイプを中心に、しっかりした食事や軽食タイプなど味や種類が豊富に出ているので、個人の目的に合わせて手軽にタンパクが取りやすいメリットがあります。
タンパク質は免疫維持に役立つ
タンパク質は筋肉への効果が注目されがちですが免疫細胞の材料でもあります。
そのため、タンパク質を日常的に必要な量をしっかりとることで、免疫を良い状態で維持することが可能です。
また、日常的な免疫の維持のほか、免疫細胞の中でも病原菌を排除する働きある「キラーT細胞」の活性化にもタンパク質が必要になります。
普段からダイエットやボディメイクのために摂取しているタンパク質には、こういった効果もあるのです。
風邪をひいたら?回復には栄養補給と睡眠が重要

風邪は誰しもかかる病気であり、一般的な対処方法は市販薬の活用・消化吸収の良い食事と水分補給・十分な睡眠であることはご存知かと思います。
症状が重篤なら、医療機関にかかりましょう。
風邪の時のプロテインは、栄養や水分補給などに活用できる場合もあるので、状態に合わせて無理なく取り入れてみてください。
消化吸収の良い食事と水分補給が必須
風邪の際は消化器官が弱っていたり食欲が落ちやすいので、胃腸に負担をかけずに体を温める食事をとり、しっかりと水分を取ることが大切です。
一般的には以下のような食材をとることが推奨されます。
| ビタミンが取れる食材 | にんじん、ごぼう、かぶなどの根菜類、じゃがいも、さつまいも |
| 体を温める食材 | しょうが、ねぎ、にんにく |
| 栄養価が高い・消化のよい食材 | 卵、豆腐、ヨーグルト、白身魚 |
これらの食材を使っても、揚げたり炒めたりと油を多用する方法で調理してしまうと胃腸に負担をかけてしまいます。
そのため、調理方法は「煮るか蒸す」で、具は小さくカットして火が通りやすいようにし、香辛料や刺激の強い調味料を避けるようにすると良いでしょう。
上記を使った調理一例
- おかゆ、柔らかく煮たうどん
- 根菜や鶏肉をいれたスープ
- お味噌汁
固形物を食べるのが厳しい場合は、スープや温めたドリンクタイプのホエイプロテイン(※1)が役立ちます。
手軽にカロリーやタンパク質が取れると同時に水分補給も行えるので、体を冷やさないように(※2)50℃ぐらいのぬるま湯で温めて飲むと良いでしょう。
※1:ホエイプロテインは消化吸収が素早く胃腸に負担をかけにくい。乳糖不耐症の方はソイプロテインの選択もあります。
※2:栄養素に影響はないものの、プロテインは熱いお湯により溶けにくく固まる(ダマ)になることがある。
十分な睡眠・休息をとる
睡眠は体をメンテナンスする時間であり、風邪をひいていなくても日頃からしっかりとることが大切です。
特に免疫力は睡眠中に向上するので、質の良い睡眠(深い眠り)は風邪の改善に必要となります。
まず、食べられないなら電解質の水分補給だけはしっかり行うことを優先してください。
ただし、風邪と闘ってる最中の体はエネルギーを必要としているため、「食欲はなくても空腹感がある」という状態になることがあり、睡眠を浅くしてしまうことがあります。
もし水以外に味のついたものを口にできそうなら、プロテインを寝る1時間〜30分ぐらい前に飲むと睡眠中のエネルギー切れを防ぐとともに、深い睡眠をえることが期待できるでしょう。
また、普段から寝る前にプロテインを飲むのもおすすめです。詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしてください!
関連記事:プロテインは寝る前に飲むべき!その理由と具体的なタイミングを解説
風邪を引いた時のプロテイン摂取のデメリットと注意点

お腹・熱・喉など、風邪にも種類があり症状も様々です。
プロテインは免疫細胞の材料、免疫機能の維持に役立つ栄養素ですが、風邪の時にたくさん飲んだからと言って体調回復を早めるものではありません。
むしろプロテインを必要以上多くとったり、体調が悪い時に無理してとることで体調を悪化させる恐れもあるので、心配なら飲まない選択をしましょう。
プロテインを飲む場合は、タイミングと種類に注意が必要です。
無理をしてプロテインを飲む必要はない
お腹の風邪=胃腸機能が低下している場合、プロテイン摂取が消化器官に負担をかける恐れがあります。
胃の不快感やお腹の不調が強い、食欲が著しく低下している時は、プロテインを無理に摂取しないほうが良いでしょう。
脱水を防ぐため電解質の水分補給が最優先であり、栄養補給はもちろん大切ですが、それが原因で下痢や嘔吐を起こしたり悪化するようであれば本末転倒です。
日頃からトレーニングとプロテイン摂取の習慣がある方は、タンパク質不足による筋力の減少(維持しにくくなる)が気になるかもしれません。
個人差はありますが、風邪が治るまでの期間は平均7〜10日間程度であり、 筋肉は形状記憶で回復しやすい特徴があります。
多少、筋肉が減少したとしても風邪が治ってから十分リカバリーできますので、特にお腹の風邪の症状がある場合はプロテインを無理して飲まない方が無難です。
飲むタイミングやプロテインの種類を選ぶ
プロテインの種類は主に、ホエイ・ソイ・カゼインの3種類ですが、消化が早く負担をかけにくいのはホエイプロテインになります。
風邪をひいた際には、胃腸機能も弱っている場合が多いので消化しやすい食事の際に、プロテインも摂ることができれば消化の負担を軽減することができるでしょう。
また、上記「十分な睡眠・休息をとる」でお伝えした通り、寝る前の1時間から30分前にプロテインをのむと、睡眠を妨げる空腹感を解消しつつ、栄養と水分もまとめて補給できます。
消化の負担を軽減するためにも、「プロテインを摂るなら風邪の最中は食事と一緒の方が良い」とお伝えしましたが、難しければ無理にこのタイミングに合わせる必要はありません。
飲めるタイミングで少量ずつ飲んだり、症状が軽くなり回復してからとるようにしてください。
体調回復後の運動は慎重に!医師やトレーナーに相談もあり
この記事では、風邪を引いた時にプロテインは飲んで良いのか?をテーマに、プロテインの基本的なメリットと風邪の時に取る際のデメリット・注意点をまとめていきました。
プロテインは筋肉の維持だけではなく、免疫維持にも役立ちますが、風邪の時に大量にとっても回復を早めるような効果はありません。
症状(お腹の風邪)によっては、体調不良をより悪化させてしまう可能性が高いので、無理して飲むのはやめましょう。
もちろん「症状が軽い・食欲不振だが食べられないほどではない」そのような場合は、水分補給と栄養補給がまとめて行えるメリットもあります。
トレーニング習慣がある方は、風邪が治ったらまたプロテイン摂取とトレーニングを再開すると思いますが、体調回復後の運動量・内容は慎重に検討しましょう。
どれぐらいのスパンで、サプリや食事、運動量を戻していけばいいのかなど、気になることがあればトレーニングのプロに相談してみませんか?
当ELEMENTジムは、トレーニングや食事指導などの専門知識をもったプロ(または早期資格習得を目指すトレーナー)が在籍しています。
個別指導なのであなたの状態に合った、アドバイスが受けやすい環境ですし、1回30分の時短トレーニングでサクッと体調管理もできます。
気になる方は、ぜひ随時開催中の体験レッスンにお越しください。お気軽なご参加をお待ちしています。